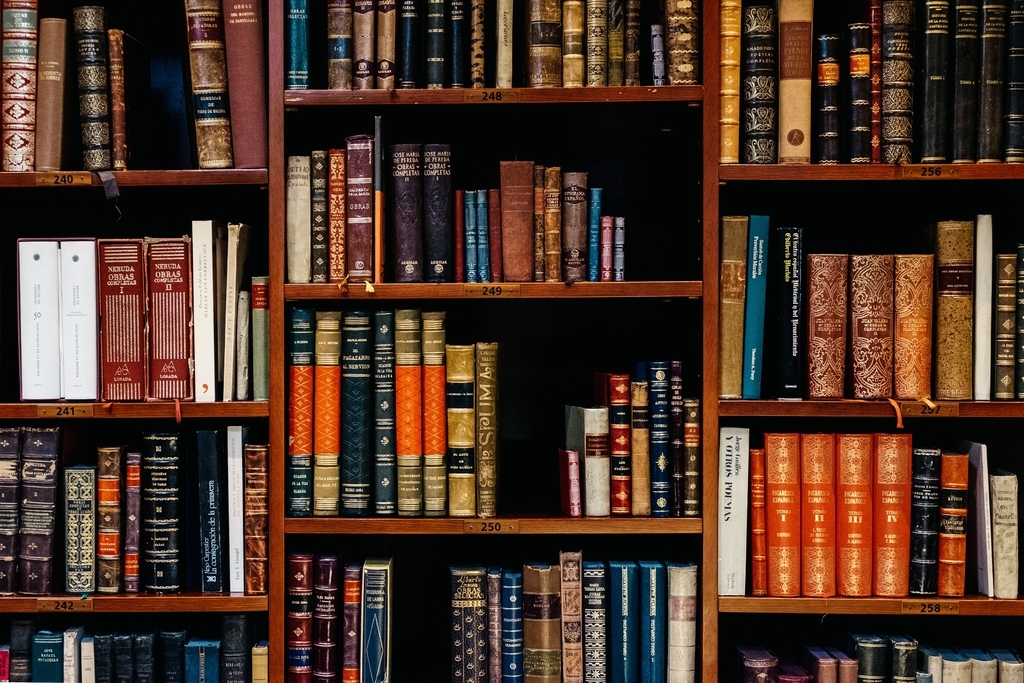
小学校に入ってしばらくは、子供はもちろん親も新しい生活に慣れるのに一生懸命で、あまり余裕がなかったのですが・・・ケイの小学校生活が軌道に乗ってくると、色々と細かいことについても考える余裕が生まれてきました。
そこで本格的に考えたのが、本来の学年より上の学年の内容を学習していく、先取り教育についてです。幼稚園時代にケイの好奇心の赴くままに算数の先取りは進めてきて、その過程では早期教育のメリットとデメリットについて、色々と考えることが見つかりました。しかし、小学校入学後に先取り教育について考え始めたのは、ケイの家庭学習で生まれてきた新しい問題がきっかけでした。
十分な家庭学習時間が確保できないという問題
無事に小学校へと入学したケイ。新しい生活にも慣れていき、帰ってきたらとりあえずその日の宿題とZ会ハイレベルの国算1日分をしっかり終わらせることも習慣化することができました。しかし、順調に進んでいるように見えたケイの家庭学習に、思わぬ問題が持ちあがります。学校の宿題とZ会の教材では、家庭学習の時間が十分に確保できないことがわかってきたのです。
小学生の家庭学習の時間は、(学年+1)×10分が目安だとか、できれば1年生でも30分ほど集中して机に向かっていられるのが理想だとか言われています。しかしケイの場合、毎日の学校の宿題とZ会の教材の家庭学習では、10分もかからず終わってしまい、明らかに習慣化する勉強時間として物足りない量になってしまいます。
家庭での学習習慣の確立には、毎日机に向かう習慣づけと同時に、集中して机に向かっている時間を長くしていく訓練としての意味合いも非常に重要だと考えられます。その点で、宿題とZ会教材による家庭学習だけでは、ケイに十分な家庭学習の時間を確保し、集中してある程度の長さ勉強する訓練を積ませることが難しいのは明らかでした。
家での十分な学習時間を確保するための方法
ケイの家庭学習の時間をもう少し確保するためには、それ相応に歯ごたえのある課題を用意することが必要です。そこで、どんなことをすればケイが退屈せずに家庭学習の時間を伸ばしていけるか、可能性のある作戦を考えました。
1年生の学習内容で分量を増やすのは難しそう
ひとつは、あくまで1年生の学習範囲を逸脱せずに勉強量を増やしていく方法です。ケイが宿題とZ会で取り組んでいるのは、どちらも1年生の算数と国語です。それで10分以内に勉強が終わってしまうということであれば、単純に今の3倍程度の量をやってもらえれば、30分の勉強時間が確保できるということになります。
しかし、同じような問題を単純にたくさんこなすと、公文式的なやり方に近くなってしまいます。公文式は私も子供のときにやりましたが、単純な問題の反復は非常に退屈で、勉強がとても義務的に感じられるので、子供にはやらせたくないと感じていました。
単純な問題の量を増やすという方法の他には、1年生の学習内容でより高度な内容の問題に挑戦させるという戦略もあります。しかし、Z会のハイレベルはすでに学校の教科書よりも難しい内容を扱っています。同じ1年生の勉強内容でそれ以上に難しい問題ということになると、中学受験対策の塾から出ているドリルなどを選ぶことになります。
しかし、四則演算など基本的な内容しか勉強しない低学年の間は、高難易度の問題と言っても文章が少し複雑になる感じで、たかが知れています。低学年で学習する限られた内容で面白い問題をたくさん作るのは難しく、ドリルをやっても結局似たような問題を繰り返しやることになってしまいそうだと思いました。
上の学年の内容を先取り学習
もう一つの手は、1年生の内容に拘らず、上の学年の内容を先取り学習してしまう方法です。上の学年で学習する内容であれば、初めて学習する内容になるため当然難易度は上がり、家庭学習の時間を確保するには十分な難易度は、簡単に達成できると考えられます。
しかし、「できるから」で先取りすると、先取りが上手く進まなくなってきたときに色々面倒なことになるということは、幼稚園時代の九九学習で体験しました。特に問題になるのは、子供が「なんで学校でまだやらない勉強をするの?」と聞いてきた時に、子供が納得できる理由です。
「十分な家庭学習時間を確保するため」というのも、十分な理由にはなると思いますが、色々考えていた結果、先取り学習にはケイにとってもっとポジティブな意味が見出せると思いました。
ケイの世界を広げるための先取り学習
ケイはとにかく知的好奇心の塊のような子です。物事の仕組み、言葉の意味、英語でなんと言うか、その言葉は何語なのか、どういう漢字を書くか、書かれている数字の意味などなど・・・ケイの1日は、とにかく疑問と質問であふれています。
しかし、知りたいことが溢れているこの世の中で、ケイが自分の知りたいことを知り、わからないことを理解していくためには、どうしても今よりもう少し進んだ知識が必要です。
どういう漢字を書くかを説明しても、その説明した字自体を知らなければ、理解できません。四則演算がわからなければ、三角形の面積の求め方を説明しても理解できません。1年生で学ぶ知識では、クイズ番組すら満足に楽しめないのです。ケイはクイズ番組が好きでよく見ますが、小学1年生の知識だけで解ける問題というのはほとんど出てきません(それでもクイズ番組が大好きというのが、ケイの面白いところではありますが)。
好奇心と知識レベルのアンバランスさは、日ごろケイを見ていて強く感じます。ケイは、ケイが今持っている知識では答えを理解できないような、進んだ質問をたくさんしてきます。とても本質的で良い質問なのに、ケイがその答えを理解するための知識を持つのは、何年も先のこと、そんなもどかしい場面が、毎日のように訪れます。
先取り学習は、このケイの好奇心と知識レベルのアンバランスさを解消し、ケイがこの世の中をもっともっと楽しめるようになるために、大いに役に立ってくれるのではないかと考えられました。
先取り学習が勉強の面白さを伝えてくれる可能性
さらに、先取り学習はケイに、自分で好きなことを勉強する大切さや面白さを伝えてくれる可能性が高いのではないかとも思われました。
先取り学習は学校で先生に言われて皆するという、義務的なものではありません。別にやらなくても良い任意の、いわば「余計なお勉強」です。しかし、勉強というのは本来やりたいから、楽しいからするものです。そういう意味では、より任意性の高い先取り学習の方が、義務的な勉強よりも、より勉強というものの本来の姿に近いのです。
先取り学習の結果身につけた進んだ知識で、もしもケイがクイズ番組をより楽しめたり、より複雑な世の中の仕組みを理解できるようになったならば。それは「学校の勉強ではない勉強で自分の世界が広がった」という実感として、より主体的で能動的な勉強への意欲につながっていく可能性が高いと考えられます。
先取りのデメリットの発生がいまのところ無い
先取り学習には、学校の授業が面白くなくなり、退屈する結果不真面目な授業態度を生み出してしまうというデメリットも懸念されます。しかし、幼稚園で進めてしまった算数の先取り学習の影響を見ている限り、ケイの場合そうした問題の発生は無いようでした。
算数と英語の先取りを進めてみる
懸案だった「なぜ先取り学習をするのか?」には、それなりに納得してもらえそうな理由が考えられました。そこで、先取りしたらケイにとって一番面白そうな内容は何かを考えた結果、それは算数と英語ではなかろうかという結論になりました。
ケイの大好きな算数と学校提供の家庭学習教材という後押し
算数はケイが一番好きな科目で、一番得意な科目です。先取りを進めるモチベーション的にも、教える親の負担的にも一番都合が良いと考えられます。また、先取り学習で急激に勉強の負担が増えたりするのも困るので、本人の能力的に負担が少ない算数は、そうした心配がない分、導入が簡単そうでした。
さらに心強かったのは、ケイの小学校が提供してくれる家庭学習支援教材の存在です。ただの公立小学校にまさかそんなサービスがあると思っていなかったのですが、ケイの小学校では、6年生までの算数の各単元について、家庭学習支援教材が整備されているのです。
この教材はあくまで家庭学習支援教材で、別に先取り教育用の教材として準備されているわけではないのですが、別に先の学年の分を進めても問題ありません。しかもこの教材、きちんと確認用テストもついていて、結構よくできているのです。ただの公立小学校なのに、本当にサプライズでした。
何より素晴らしいのは、この教材は節目まで終わったら先生に提出すれば、「終了シール」がもらえるということ。このシステムならば、学校の先生に自然に先取り学習の状況を伝えることができてしまいます。
学校公認の教材で、先生に進度を伝えながら先取り教育可能であれば、先取り学習のデメリットが出てくる可能性を、減らすことにもつながることが期待できます。そこで、算数の先取りは、この学校の教材を使って勧めることに決めました。
1年生の夏休みに2年生の算数まで終了
学校提供の教材を使った家庭学習は1学期の終盤にスタートしたのですが、1年生の内容は一か月かからず終わってしまい、2年生の内容も夏休み中に終わってしまいました。1年生の2学期からは、3年生の学習内容を進めています。
英語学習はチャレンジイングリッシュでゲーム感覚に
ケイは普段からアルファベットを見ると「どこの国の言葉か」「なんという意味か」を聞いてきたりと、外国語に非常に興味を持っています。さらに、他人への好奇心が非常に強いケイにとって、より多くの人とコミュニケーションがとれるようになる英語というツールへの学習意欲は非常に高いものがありました。
また、英語が理解できると、英語の文章を読んだり、英語で情報収集ができるようになったりと、さらに世界は大きく広がります。ケイの世界を広げるという意味では、先取りするのに非常に適した内容であると考えました。
英語の学習には英会話塾や色んな通信教材の体験を試してみましたが・・・最終的に選んだのは、オンライン教材のチャレンジイングリッシュでした。チャレンジイングリッシュはリーディングやリスニング、ライティング、スピーキング、単語、発音などの勉強を、ゲーム感覚で進めていける非常にユニークな教材です。
発音も、マイクに向かってしゃべったものを音声解析して採点していて、実際に発音がが上手な人がやると、きちんと高得点が出ます。また、月に一度外国人の先生とのオンライン英会話レッスンもついていて、読み書き会話をバランスよく伸ばしていけるのが心強いです。
他のDVD視聴がメインの教材に比べて、チャレンジイングリッシュはゲームやクイズの要素が満載なところに、ケイがハマったのでした。毎日非常に意欲的に取り組んでいて、今はチャレンジイングリッシュ的には小3相当のレベルあたりにいるようです(問題文に読み仮名無しで出てくる漢字で判断しています)。
漢字の先取りをしない理由
ケイは漢字も好きなので、漢字の先取りも考えたのですが、結局見送りました。理由としては、漢字の読みは読書やテレビ、算数や英語の先取り学習の中で、問題文に含まれる漢字から先取りが進むであろうと考えられたため、あえてやる必要がないと判断したこと、また、漢字の書きは書き順や、正しい書き方を教えるのが親への負担が大きいという問題があったためです。
これまでのところ順調な先取り学習
算数と英語の先取り学習導入によって、30分から1時間程度の家庭学習時間を確保することができるようになりました。算数は2学年先の内容で、最近は結構てこずったり時間がかかることも多くなってきましたが、持ち前の負けん気と好奇心で、今のところめげることなくケイの学習は進んでいます。
こうした先取り学習の影響や効果がどんな風に出てくるかは、またもう少し見ていかないとわかりません。先取りの進度や気づいたことについては、また折を見て記事にしていきたいと思います。
<その他の先取り学習関連記事はコチラ>